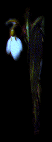
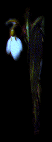
| 彼女が描くのは、ほとんどが海の絵だった。 蒼空を映して穏やかに広がる海、残照に映え朱色に染まる海、 強風と雪を巻き込み哮り狂う海、巨岩の根元を音もなく渦巻く海、 岩と岩との間に取り残された、小さな海。 彼女はおびただしい数の海の絵を描いた。 そして死ぬ前も、薄いスケッチブックを抱え、ベッドの上で海の絵を描いていた。 わたしが2度目に病室を見舞った時、彼女はベッドに半ばうずもれて横たわっていた。 前にも増してやつれている。 「仕事、どう?」 「なんとか慣れてきた。あんたはどう?調子」 「最悪。」 彼女は笑って言った。 また手術かもしれないんだって。もうしなくていいって言ったのにね。」 骨張ったてのひらを顔の上にかざした後、彼女は枕元にあった夏みかんを一個取り わたしに放った。 夏みかんを剥く 鬱金色の霧が立つ。 柑橘の芳しい香りを、惜しむように吸い込んだ。 「あのね、絵里子が5月に結婚するんだって。」 「そう、高校時代からつきあってたあの彼と?」 「それがね、彼とは去年別れたんだって。それからすぐお見合いしたらしいわよ。」 「へぇ〜、わたしたちは腐れ縁だとか言ってたのにね。」 「彼女さ、いまはもう全然描いてないらしいわよ。そういうわたしも ちっとも描けてないけど・・・」 「描いてないの?」 「勤めてからはさっぱりよ。」 「そんなに忙しい?仕事。」 「時間がないわけじゃないけどね、描く意欲がなくなったみたい。」 「亜弓らしくもない。あの頃はあんたが一番描くことに熱中してたじゃない。」 「学生の頃が懐かしいわね。絵を仕上げるのに徹夜したり、他の子たちは 遊びに行ってるのに、おしゃれもしないで、絵の具まみれになってさ。 そのうち、何も描けなくなって、描きたくなくなって、それが当たり前になっちゃって それで年とっちゃうのかな。」 剥き終わった夏みかんを渡そうとした時、彼女は爪を噛みながら窓の外を見ていた。 「ねぇ、絵を見せて。」 彼女は無言のまま枕の下からスケッチブックを取りだし、わたしの前に開いた。 海の素描(デッサン)だった。 「病室じゃ絵の具使えないから、色は付けられないんだけどね。」 画用紙に、放り出すように描かれた風景。彼女独特の、線の細いタッチ。 緩やかに湾曲した海岸線と、海に流れ込む川。 なぜかはしらない・・・・でもはっきりと、わたしにはデッサンから匂い立つ 彼女の焦りといらだちを感じることができた。 そしてそれを見透かしでもしたかのように、彼女はわたしの手からスケッチブックを とりあげ、また枕の下にしまいこんでしまった。 「亜弓はよく人物画描いてたよね。絵里子は静物画ばっかりだったし。 真澄はなんだかわけわかんない絵、描いてたっけ。」 「真澄は自分でもなに描いてるかわかんなかったのよ。それでも結構楽しんで たよね。」 あの頃・・・・高校の美術部で絵に熱中していた友達は、どうしているのか。 美大に進学した子、画廊に就職した子、絵とはまったく関係のない方面に 進んだ子。 あの頃の仲間のうち、描き続けている者は何人いるんだろう。 そしてわたしは、何をしてるんだろう。 |