

| 幾日かが過ぎた。 千手丸の体調はほとんど回復し、無理さえしなければもういつでも出立できるくらいになっていた。 千手丸が回復するまでは見守りたいとの意向で月小夜の館に逗留し続けていた葦若夫婦も、そろそろ 帰途につかねばならないはずであった。 露草はなにとはなしに気がかりだった。 月小夜の館に留まって以来、日を追うごとに夫葦若の様子が微妙に変化していることに気が付いていたからだ。 あんなに先を急いでいたはずなのに。 商いが気がかりだから、早く戻らればならないと口を開くごとに言っていたのに。 なぜもうとっくに恩人の千手丸が回復しているのにもかかわらず出立しようとしないのだろう。 しかもこのところ夜中にふと目を覚ますと、かたわらに眠っていたはずの夫の姿が消えていることがたびたびあった。 小用だろうと最初は気にも留めなかったが、しだいに露草の心を浸食してくる真っ黒いどろどろした不安は どうにもこうにも押さえきれなくなってきたのだった。 「お前さま・・・・?ねぇ お前さま。」 「なんだ?」 「千手さまもだいぶお体を回復なされたご様子。そろそろわたしたちも故郷(くに)に帰りませんと」 「ああ、わかっている。」 夫の答えはそっけなかった。 こんなにそっけない返事をする男ではなかったはずなのに と、露草はまた不安になる。 「商いが気にかかるともうされていたではありませんの?」 「お前が気にすることではない。」 「どうなされましたの、なんだかお前さま 最近変わられました。」 「なにを言うておる、わしのどこが変わったと言うんだ。」 「いいえ、変わられました。その物言い、ここに来る前はそんな冷たい物言いはなされませなんだ。」 「もういい!お前はだまってわしの言うとおりにしていればいいのだ。」 「お前さま!」 いつになく怖い顔で露草の側を離れようとする葦若に露草はすがった。 「お前さま!ね、お願い 帰りましょう。いますぐにここを離れましょう・・・わたし怖いのです。お前さまが どこかへ行ってしまいそうで、怖いの。ね?帰りましょう 早くここを出ましょう。」 「ええい!うるさい!」 葦若は腰にすがりつく露草の小さな体を力任せに突き放した。そして床にたたきつけられた露草を 見ようともせずその場を立ち去った。 「大丈夫か、怪我はないか?」 床に突っ伏したまま泣き崩れる露草に、千手丸が手をさしのべた。 「亭主はいつからあのようになったのだ。」 「・・・・・・・・いつのまにか・・・少しずつ」 「亭主はここを離れとうない様子だな。」 なにかを確認するように千手がつぶやいた。 「なにかを見極めようとするなら今だぞ、露草。それを逃したらもう取り返しがつかぬかもしれん。」 「それはどういう?」 「その目で真実を見極めるんだ、わたしが力を貸そう。」 露草はまだ充分幼さの残る顔をあげると、千手の手を握りしめて唇を噛んだ。 その夜 露草はまんじりともせず夜具の中で息をひそめていた。 『なにかを見極めようとするなら今だ』 千手丸の言葉を心の中で何度も繰り返す。 それを逃したら取り返しのつかないことに・・・・・でも、もはや取り返しがつかないのではないか。 もうどうあがいても抜け出せぬ妖しい糸にからめとられてしまっているのではないか。 そんな不安が襲う。 ほんの一瞬 露草は睡魔にあがらうすべなくまどろんでしまった。 (あ いけない。) 寝返りを打つふりをして夫のほうを向いた。 夫はいない。確かにいましがたまで露草の隣で寝息をたてていたのに。 たった一瞬露草がまどろんだ隙に夫の夜具はもぬけのからになっている。 露草は意を決して部屋を抜け出した。 すぐに向かったのは館の女主人の寝屋。 あそこにいる 夫葦若はあそこにいると確信めいたものが露草を突き動かしていた。 館の奥の月小夜の寝屋。 恐ろしいほどしんと静まりかえる。見るのが怖い。あの中を見てしまったら、それまでのささやかな幸せが 一瞬にして消えてしまう。露草はたちすくんだ。 「露草 自分の目で見極めるんだ」 背後から千手の低いささやきが聞こえた。 「千手さま・・・・・」 「見ぬままですまされまい。おそらくもはや取り返しのつかないところまで来ているやもしれん。それでも 見ぬままではすまされぬぞ。」 露草は震える手でそっと寝屋の戸を開けた。 ねっとりとした宵の闇がたちこめる部屋の中。うっすらと月の光だけが差し込むその中に、露草は見た。 夫葦若と館の女主人月小夜の姿であった。 葦若の体の下で黒髪を振り乱して歓喜する女。 「葦若・・・・・・」 女がくぐもった声で夫の名を呼ぶ。 「咲耶」 葦若がそれに答える。 咲耶?それはいったい誰の・・・・・そしてやっと千手はその名を以前どこで聞き覚えたのかを思い出した。 (奴か・・・・?) 「ああ・・・・葦若 もっと もっと強く抱いて、もっと深く」 さくや・・・・・・さくや・・・・・・さくや・・・・・・さくや・・・・・・・ 何度も何度もその名を呼ぶ。呼びながら気が狂ったように女の体を突き上げる葦若。 「いや・・・・いやいや!やめて!」 千手丸が止めるいとまも無く、露草は叫びながら月小夜と葦若が痴態を繰り広げる場所へ飛び出して行った。 「これは!?これはいったい!お・・・・お前さま・・・・」 葦若がどろんとよどんだ目で露草を見た。 「なにかの間違いだと言うてくださりませ・・・お願い」 涙でぐしゃぐしゃになった顔で露草は力無く懇願する。しかしその悲痛な声も葦若の耳には入らぬ様子だった。 月小夜はあられもない姿を隠すでもなく、不適な笑みを浮かべて哀れな露草の様子を見ていた。 「もう遅い 我が願いはかなった。」 そう言い放つと月小夜はその青白い冷たい裸身を震わせて高笑した。 「なにものなのだ、咲耶。そなたは以前わたしの生き血と生き肝を捕って食らおうとしたあの妖婆だな?」 「いかにも。」 月の光に照らし出されて、月小夜 いや 咲耶の艶めいた顔がこの世のものとは思えぬほど美しく恐ろしく 邪悪であった。 「わたしははるか昔この地を治めた豪族更科実明の末娘、咲耶(さくや)。」 「豪族の息女ともあろうそなたが、なにゆえ妖魔となった。」 「われを妖魔と申すか。」 「人の生き血をすすり、生き肝を食らう、せんだって草はらで見たあの面妖な光景、あれは そなたが旅人の血と生き肝を食ろうていたのだろう?」 「そうせねば300年生きておれなんだ!葦若の帰りを待つためには、妖魔にこの身を捧げねば生きれなんだ。」 咲耶の美しい顔が一瞬苦痛に歪んだ。 「葦若は、必ず迎えに来ると言い置いて東国へ旅立ったのじゃ。東国で商人として身を立て 必ず迎えに来ると。」 「葦若一族の先祖は元は豪族更科家に仕える下僕だったと聞いた・・・・・」 葦若がつぶやくように言った。 「更科の姫君と道ならぬ恋に落ちた下僕は実明の逆鱗に触れ、追われるように東国を出奔したというのだな?」 千手丸に、咲耶が深くうなづいた。 「わたしは待った ずっと待ち続けた。何度葦若を追って東国へ逃げようとしたか。何度も父に軟禁され それでも待ちきれず館を抜け出し東国に向かった。たったひとり、着のみ着のままで 葦若に逢いたい一心で。東国は遠かった・・・・遠すぎた・・・・・。旅の途中、東国まで 連れていってやると騙されて、口にもできぬ酷い目に合わされた。一度や二度ではない。 あのような辱めを受けて、もう生きてはおれぬ、死んでしまおうと思った。それでも死ねなんだ、葦若に逢わぬうちは どんな目に合うても死ねなんだ。」 月小夜 いや 咲耶の朱い唇が苦痛に歪む。しかし次の瞬間にはふたたび不適で邪悪な笑みに変わり その青白い全身からさらにまがまがしい光の炎が放たれはじめ、あたりの空気があきらかに変った。 周囲の闇がねっとりと生暖かい湿り気を帯び始め、生き物のようにあちこちにまとわりつく。 「おお・・・・・わたしの中に・・・・。」 と、咲耶が歓喜の声をあげる。 「ついに宿った!わたしの中に 葦若の子が宿った!わたしにはわかる。今 この瞬間 われの望みはついに 成就した!」 「いやっ!!いや!いやぁぁっ」 露草の絶叫にも近い悲鳴が闇を切り裂く。 「もののけが・・・。」 千手丸が持っていた太刀を服抜くやいなや、咲耶めがけて斬りつける。 しかし咲耶は身をひるがえし、次の瞬間には戸外に移動してしまっていた。 いつのまにか血のように真っ赤な月。 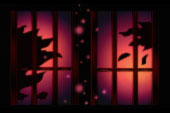 後を追って千手丸が戸外に出る。 赤い月の天空にただよう咲耶。そしてその長い髪が無数のくちなわのように四方八方にうねうねと広がる。 「千手よ、そなたに頼みがある。」 「聞かぬっ!」 「いいや、聞いてもらう。そなたの腹を借りるぞ。」 「なにをたわけたことを・・・・」 咲耶の髪のひと房がするすると伸びて千手丸の体を捕らえようとする。とっさに髪に斬りつける。 しかし何度切っても 切った先から髪は伸び ついには千手丸の体を捕らえた。 「さぁ わたしの胎内に宿った葦若とわたしの子をそなたの腹に送るぞ。」 「な、なにを!?」 「子はそなたが産むのだ。わたしと葦若の子を・・・・」 千手丸の体を虜にした咲耶の髪を通して、なにか温かいものが体の奥底に流れ込んでくるのがわかる。 生暖かい体液のような、血のような、涙のような・・・・・・ 「300年もの間 待ち続けて 待ち続けて いまやっと葦若と相まみえることかなった。これでやっと 消えることができる。」 妖気ただよっていた咲耶の顔が、月小夜と名乗っていた時の優しげで穏やかな顔に戻っていく。 「この葦若は、そなたが愛した葦若とは違う!!」 露草が絶叫した。 「300年前の、祖先のことなど知らぬ、この人はわたしの夫、そなたの思う葦若ではないっ」 「血よ。そのものの中に脈々と流れるその血はまぎれもなく、わたしが愛した葦若の血。」 そして咲耶がその両手を葦若に向けて差しのべた。 「会いたかった ずっとずっと この身は妖しの物と成り果てても。お前を愛していた。 われが人間だった頃 お前の子が欲しいと願った。いまやっと願いがかなった。」 千手丸の体をいましめていた咲耶の髪の毛がするするとほどけ、千手丸はどさりと地面に投げ出された。 「今度生まれてくる時は・・・・」 その言葉の続きはふいに吹き出した強い風でかきけされた。 咲耶の両手が虚空をかき抱く。家を取り囲んでいた野茨(のいばら)のツルが生き物のように 這い寄ってきて咲耶の全身を取り巻く。野茨の青く硬い棘の一本一本が咲耶の肌に食い込むと その葉と葉の間から咲いていた真っ白い花がしだいに朱に染まっていくのがはっきりとわかった。 咲耶の美しい姿態はみるみるうちにその野茨に精気を吸い取られ、しわがれ、ついには 一陣の風に跡形もなく吹き上げられていった。 あとに残ったのは静寂。なにごともなかったかのようなねっとりとした闇。赤い月。  |