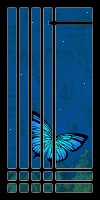

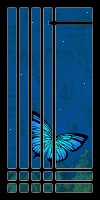

| 最初の夜が更ける。 外からは虫の音だけがかすかに聞こえる。 格子から見える月は凛として、研ぎ澄まされた獣の爪のようにも見える。 ほの暗い部屋の中で、囲炉裏の側だけが赤々と燃える炎で明るい。 月小夜が、その明かりの下で着物を縫っていた。 時折、格子からかいま見える上弦の月を見上げ、しばし放心したように月に見入っているが、 ほどなくしてまた縫いはじめる。その姿はなぜか楽しげに見えた。 「精がでますね。」 もうとっくに露草と共に寝入ったと思われていた葦若が、囲炉裏の側に腰を下ろしながら話しかけた。 「早く仕上げないと・・・・わたしは手がのろいのでいつまでたってもできあがりません。」 「男物と見受けましたが、ご亭主の?」 「はい、所要でもうずっと長い間遠国に出向いております。」 「ほぉ、それはお寂しいことでしょう」 「いいえ、寂しゅうはございませんよ。いずれ必ず帰ってくると約束したのですもの。それに離れていても 心はいつも一緒ですから。」 そう言って、月小夜はにっこりと笑った。 月明かりに照らされて、その瞬間月小夜は神々しいくらいに美しく見えた。 「これはこれは、あてられてしまいますね。ご亭主がうらやましい。このように美しい女房どのを置いて家を離れているのは さぞかしお心残りでしょうなぁ。1日も早いご帰還をお祈りもうしておりますよ。」 「ありがとうございます。・・・・白湯でもお入れいたしましょう」 月小夜は囲炉裏の鉄鍋に沸いた湯を、ひしゃくで茶碗に汲みはじめた 「ご妻女はお休みになられましたの?」 「ええ、今日一日の疲れがどっと出たようで、床に入ってすぐに寝入ってしまいましたよ。わたしは逆に 目が冴えてしまって、なかなか寝付かれません。」 月小夜が手渡してくれた白湯を飲みながら、葦若はとつとつと話し始めた。 「この地は昔 大変栄えていたと聞き及びます。月小夜殿はご存じか?」 「はい、もう300年も前のことらしゅうございますけど、当時はあまたの人が住み 市もにぎわい それはそれは活気あふれる土地であったと・・・・」 「ここを治めていた豪族が滅びて後、この地に住む者たちも離れ、廃れていったという。」 「葦若さまはどうしてそれを?」 「わたしの祖先はこの地で生まれ そしてここを離れて東国に住み着いたのだそうです。」 「まぁ・・・・そうでしたの。」 「ここはわたしたち葦若一族のゆかりの地なのですよ。今は昔の名残も無く鄙びてしまってはいるが やはり血は故郷を懐かしんで騒ぐものらしい。ここに足を踏み入れてからずっと、そこかしこが懐かしい。 わたし自身は当然この地の記憶などないはずなのに。」 「人とは不思議なものですわね。」 月小夜はつぶやくように言った。 「人は死に 肉体滅びて記憶は失われても、子から子へ受け継がれていく血というものは生きた記憶を 引き継いでいくものなのでしょうか。」 「ほんに・・・・そんなものなのかもしれません。」 「どんな記憶も 血が引き継いでくれるというのでしょうか。」 月小夜のつぶやきは、あまりにかすかすぎて葦若の耳には届かなかった。 夜だけが、深々と更けていった。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あしわか・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 深い暗闇の向こうから呼ぶ声がする。 「誰だ、わたしを呼ぶのは誰だ・・・・・」 ・・・・・わたしのことを忘れたの?葦若・・・・・・ 「誰だ、そなたは誰だ、どこにおる。」 ・・・・・・ここに お前さまの目の前に。ずっと待っていたの お前さまを待っていたの・・・・・・ 漆黒の闇の果てを見据える 闇の一点に針の穴ほどの光が輝きはじめ、凝視しているとそれはしだいに 人形(ひとがた)を成していく。 よく見るとそれは女ようにも見えた。 「ずっとずっと、気の遠くなるほどの長い間 待っていた、お前さまを、待っていた」 その声はしだいにはっきりと葦若の耳に響いてくる。初めて聞く声 なのに懐かしい。 「名は?そなたの名を教えてくれ。わたしを待っていたとは?」 「わたしは咲耶(さくや) お忘れか?長い月日はあんなに愛しんで下さった名までも忘れさせてしまったの?」 咲耶 咲耶 その名に聞き覚えはないはずだった。 なのになぜこんなにも懐かしい? 「葦若 長ごうございました。ずっとずっと気がふれてしまいそうなほど長い間、お待ちもうしあげておりました。」 顔は見えぬ、ただその青白い人形だけが、妙に生々しく葦若の元につと近づいてくる。 逃げようとするが、体が動かない。顔もわからぬその人形に魅入られたように葦若はただ人形のなすがままにいるほかはなかった。 人形(ひとがた)がしなやかな両腕で葦若をとらえる。そのかいなは葦若の体をからめとり、内臓までも懐柔しようと もくろんでいるかのようだ。 「抱いてくださりませ やっとふたたび相まみえた。咲耶 愛おしいと、逢いたかったと、言うてくださりませ」 青白い体はその外観とはうらはらに、暖かかった。血の通った女の暖かさだ。 ずっとずっと昔、その暖かさをどこかで感じたことがあるような気持ちにさえなる。 葦若はいつしかその体を抱きしめていた。 それは葦若の夢であった。 寝付かれぬまま床の中でうつらうつらとしているうちに、忽然と深い眠りに落ちていたのかも知れぬ。 はっとして身を起こすと、あたりはまだ朝ぼらけの薄闇。隣には露草が軽い寝息をたてている。 愛しい恋女房のすぐ側で、なんとも不謹慎な夢を見たものよと、葦若は苦笑いした。 それでも、夢とは思えぬほど葦若の両腕には、あの青白い女の体の感触とぬくもりが残っている気がした。 「咲耶か。」あらためておのれの記憶をさぐってみても、その名に心当たりはない。 祖先ゆかりのこの土地の空気が見せた幻覚であったろうか。 |
同じ夢を千手丸も見ていた。 深淵の闇の中、葦若を抱く青白い女の影。 愛おしげにかきいだく葦若。 (やめろ、その体を離せ 葦若。) 叫んでも、その声は虚空に吸い込まれて葦若には届かない。 その人形(ひとがた)がなにものかは千手丸にもわからない、が、なにかひどくまがまがしい邪悪な気が、その体全体から 猛烈な勢いで放出されている。 (その体に触れてはならぬ!葦若、離せ!) すると、葦若におおいかぶさるようにして葦若の体にしがみついていた青白い女の体が、ゆらりと千手丸の方をふりむいた。 顔は無い。鈍い光を放つ青白い肉体には、顔は無い。しかし無いはずの顔のあたりからは、確かにニヤリと微笑む 表情が感じ取れる。勝ち誇ったような邪悪な笑みが。 その瞬間千手丸は軽い吐き気を覚えた。 目に見えぬ何者かが、今まさにひどくまがまがしい邪念を達成するべく 事を成している。 その思念が真っ正面から千手丸を襲ってくる。 (やめろ、わたしを見るな、見るな! 見るな!!!」 そして唐突に、千手丸は眠りから覚めた。 嫌な冷たい汗が全身をしたたり落ちる。 なんだったんだ・・・・あれは・・・ たくさんの寝汗をかいたせいか、熱はひいたように感じる。発熱した後の虚脱感がひどい。 千手丸はそっと床を抜け出して、土間に降り水瓶から水を飲んだ。 まだあたりは夜があけきっていない。 そのまま裸足で千手丸は外に出てみた。朝霧が深く立ちこめ、露にしっとり濡れた下草がほてった素足に心地よい。 早朝の凛とした空気は、熱がひいた後のけだるさを振り払ってくれる。 ついでにあのいやな夢もふりはらってくれまいかと、千手丸は思った。 千手丸も腰が抜けたものよ・・・・・と ひとりごちる。 たかが悪夢ごときにおじけるとは。 今までどんな時もひとりで切り抜けてきたではないか。どんな修羅場も怖いとは思ったこともない。 氷のような心でくぐり抜けていたおのれが、夢の中で見た女におじけづくとは。 その時 かすかな低い物音に気づき足を止めた。 向こうの木立の そのまた向こうから聞こえる。なんの音か、水音にも似ているが人の声にも聞こえる。 こんな早朝の人気のない草の原にはあまりに似つかわしくないその音のする方向へ、千手丸はそっと 近づいていった。 コポ・・・・・・コポ・・・・・・・コポ・・・・・・・・ 水? いや、違う・・・・・ もっと濁った、どろりとしたなにかが吸い上げられる音。 見てはならぬ と、千手の本能がささやいた。見たら二度と見なかった自分には戻れぬ、なにも知らなかった自分には 戻ることができない、だから見てはならぬ。 しかしそれでも、千手はおもむろにその音のする草むらに近づき、背の丈以上もある草をそっとなぎ倒してみた。 (あれは・・・・・・・・・なんだ?) 草原に唐突に突き立った一本の杭。真っ黒い杭。そこにわらわらとからみつく あれは荊のつるに見えた。 しかも荊のつるは生き物のようにその葉をザワリと蠢かし、からめとった杭を撫でさする。 もっとよく見ようと、千手は目を凝らした。 あの真っ黒い杭 いや違う、あれは杭ではない、人間だ。 黒い棒か杭に見えた物、それはまぎれもなく人間だった。 よく見ると、近くの地面に旅人のものと思われる荷物や衣服が無造作に散らばっている。 とすると、あの杭のような人間は、行きずりの旅人なのだろうか。 なにをどうすればあんな色に変色するのか炭のように真っ黒く、しかも全身の水分を吸い取られ、からからの 抜け殻の状態になり、おそらくはすでに息絶えているように見えた。 そのひからびて杭のようになった肉体を、なおも荊のつるがギリギリとしめあげていく。 そして無数の鋭く青い棘は、ひからびた真っ黒い肉体になおも深く突き刺さり、コポコポという音をたてながら 肉体にわずかに残った体液を吸いつくそうとしていた。 (物の怪か。) 千手は目をそばめて右手で口をふさいだ。生臭い血の臭いがそこらじゅうに漂っていたからだ。 (あ・・・・・・・ああ・・・・・・・・・・・・) 驚いたことに、とっくに絶命していたと思われていたその真っ黒くひからびた者がうめいた。 こんな萎びた杭になり果てても、まだ生きながらえていたとは。 (うう・・・・・・・・・) 不思議なことにそのうめき声は決して苦痛な響きできない。むしろ快楽の嗚咽にも似ている。 こんな状態になりながらも。 コポコポ・・・・・コポ・・・・・ 血の吸い上げられる音と、うめき声が交錯する。 千手はそっとそのままその場を離れた。 見てはならぬものを、見てしまった。このままではすまないだろうとそんな予感が千手の脳裏をよぎった。 千手丸が月小夜の館に戻ると、月小夜は既に朝餉の支度にとりかかっているところだった。 「まぁ・・・・千手どの、お外にお出になってはまだいけません。」 月小夜はかけよって、千手の体を支えようとした。 「支えはいらん、もう大丈夫だ。それよりこのへんには妖魔が出没するのか?」 「なにをおっしゃいますやら」 月小夜はそう言って笑った。 「それは都のなれの果ての地、さまざまな栄枯の怨念がそこここに渦巻いて、妖魔の一匹や二匹 巣くうてもおりましょうね。でもわたくしはまだお目にかかったことはございませぬよ?」 そしてまた、ほほほ・・と笑った。 「お熱のせいで悪夢でもごらんになったのですね、さぁ もうすぐ朝餉ができまする。もうひと眠りなされませ」 千手丸は食い入るように月小夜を見た。 昨夜までの月小夜とはどこか違う。 最初から美しい女ではあった。しかし今目の前の月小夜は、薄い膜が一枚剥がれ落ちたかのように 艶めいて見える。 (そなたは なにものなのだ・・・・・・) その言葉を千手丸はぐっと飲み込んだ。 |