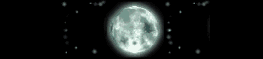
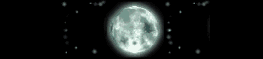
重衡は一日の大半を森で過ごすことが多かった。
狩野介は重衡にたいそう好意的で、平家の囚われ人である
重衡をあたかも客人のごとく丁重に扱っていた。
軟禁するでもなく、見張りをつけるでもなく、自由な日々を
提供していた。
千手丸を助けてから、10日ほどがたとうとしていた。
木々のざわめきに身を浸していると、重衡は己がどこの
何者なのか忘れそうになる。
そんなとき、麝香鹿が遠くの木陰に立ちつくしていることがあった。
「鹿よ、そなたに名など必要ないな。」
鹿は凛として、木々の間に同化している。
「見事な鹿だ。」
「千手丸。」
いつのまに来たのか、傷を負った左腕をだらりと下げて、
千手丸が重衡の後ろにたっていた。
「傷は痛まぬか。」
「これしきの傷、あと二日もすれば癒える。」
「無理するな。」
何気ない動作にも、無意識に傷をかばおうとする千手丸に
重衡は言った。
「麝香か、雄のはらわたからは上等の香料がとれるそうな。
望みとあらば捕らえて、我が命の恩人に捧げよう。」
「殺生は好まぬ。」
「ふん、人は殺しても鹿は殺さぬか。今まで何人を手に掛けた?」
「一ノ谷で捕らえられてから今まで、私は仏にこれまでの
己の所業を許し願ごうている。いくら悔いても我が罪は
消えぬとわかっているが。戦場の我と今の我は
違うのだ。」
「なにが違う。」
千手丸は嘲笑した。
「私は何人もの命を奪って、その金品を奪ってきた。
そうやって生きてきた。しかしただの一度もそれを
悔いたことなどない。」
「哀れな奴・・・・・・。」
「私のどこが哀れだ。」
「そなたにはわかるまい。」
重衡の声はあくまでもおだやかだった。
「千手丸よ、そなた女子であろう。」
「それがどうした。」
「なにゆえ、そのようななりをしておる。」
「知ったことか。」
千手丸はちぎった草を重衡になげつけた。
「そうやって、首をはねられる時を待つつもりか。」
そう言い捨てて、千手丸は石を拾い上げ
鹿めがけて投げつけた。
石は腹に命中し、鹿はさっと茂みに逃げ込んで行った。
「何をする。」
「ほんな見事な鹿よ、あれなら良い麝香がとれるだろう。」
そして千手丸は来た道を足早に歩いていった。