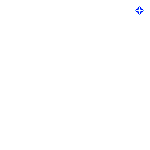
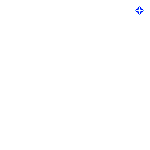
「フレイヤ、そろそろ西風が吹き始めた。夕暮れだよ。」
「そうね。」
「天幕に戻ろう。」
「ええ・・・」
そう言って手綱を返そうとした時、彼らの目前を、痩せた山羊を連れた小さなジュヌバの娘が
横切った。
「ちょっと聞きたいことがあるの」
フレイヤは馬上から娘を呼び止めた。しかし娘は振り向きもしない。
「聞こえないのかしら。」
フレイヤとシュクは顔を見合わせた。
「怪しい者じゃない、俺はラ・ダールの集落のシュク・タジミアだ。」
シュクが馬から降り、娘の後ろから肩をたたいたとたん、娘はびくっとして振り向いた。
「ちょっと聞きたい事がある。」
すると娘は自分の耳を指さして、かぶりを振った。
「ああ、そうだったのね。ごめんなさいね。」
シュクに続いて馬を降りたフレイヤは、娘に向かってゆっくりと口を開いた。
「ハーランドから来た男を探しているの。キリオン・コンラートという名の。」
コンラート・・・・・・その名がフレイヤの口から発せられたとたん、娘の顔が
こわばった。
「知ってるの?」
娘は首を振った。
「知ってるのね?知ってるんでしょ?」
なおも娘は激しく首を振り続ける。
「言って、正直に言って。でないとこれを使うわよ。」
フレイヤは腰の剣を抜いた。
「フレイヤ!やめて、それだけはやめてよっ」
気がふれたかのように首を振り続ける娘の腕を掴み、フレイヤは容赦なく問いつめた。
「お前たち!なにをしているっ」
太く力強い男の声が響いた。振り返った瞬間、フレイヤは息を呑んだ。
![]()
2人は随分長い間、互いに向かい合っていた。
「こんなところでフレーセンの姫君にお目にかかるとは思わなかった。」
皮肉ともつかぬ口調で、コンラートは言った。
「お前を探しに来た、キリオン・コンラート将軍。」
フレイヤの声は水のようにおだやかだった。
「俺を殺しにか?」
コンラートはにやりと笑った。
「お前のために、私は多くの大切な者を失った。数多くの重臣たち、その部下。
お前の率いる兵士たちは汚いやり方で彼らの命を奪った。」
「それが俺のやり方だからだ、鬼火の姫。」
「お前はまこと、あのアストライドの城で出会った、キリオンなのか・・・」
「キリオンは死んだ。お前の目の前にいるのは、ただの無頼の輩にすぎん」
その時、心配げに2人を見比べていたユラは、ふいをついてコンラートに
駆け寄ろうとした。
その体を、戦場でつちかった動物的な敏捷さでフレイヤは捕らえ、少女の細い腕を
引き寄せ、その喉に刃をあてがった。
「ユラを離すんだっ」
「なぜ・・・出奔した。将軍と、ハーランドの勇者の名を捨て、なぜ国を捨てた。」
「姫こそ、何故自ら俺のような風来坊を追ってきた?フレーセンの姫ともなれば、
鼻も目も利く手練れの者がいくらでもいたはずだ。」
「私の問いに答えるのだ、キリオン・コンラート!」
「人は王とか、名誉とか、そんなもののために戦うことはできぬと悟ったからさ。」
たまりかねて、シュクが叫んだ。
「じゃあ・・・じゃあ何のために戦うのさ!」
「おのれのためだ。そしておのれが愛する者の為だ。それ以外にない。
フレイヤ・フレーセン、その娘を離せ、そうしたら、俺はお前の手にかかってやっても
よい。それが俺の戦いだからな。」
「私がこの子を助けたら、私に殺されてもいいというの?」
コンラートは腰の剣を抜いて、足下に投げ出した。
「俺の剣はとっくにその娘に捧げているのだ。その娘は俺が守る。」
フレイヤはその美しい顔を歪め、呪うように天を仰いだ。
(君になにかあったら、僕が守ってあげる。)
はるか昔に聴いた、懐かしい声が甦ってきた。
(忘れないで、僕が守ってあげる。)
このまま手を離したら、コンラートは本当にフレイヤの手にかかって死ぬ気なのだろう。
そしてもし、このまま2人を見逃したら、今度こそコンラートはフレイヤの前から
永久に消えてしまうだろう。この娘もろとも・・・・
フレイヤは何かを決意したかのように、真っ正面を見据え、そして氷の表情のまま、
ユラの体を突き放した。
ユラの華奢な体はよろよろとよろけ、大地に倒れようとした、その瞬間、
フレイヤの剣がユラの背中めがけて振り下ろされた。
「あ・・ああっ!!」
シュクが叫ぶ。
かさりと、ユラの体が草の上に落ちた。
「ユラ!!」
コンラートが駆け寄って抱き起こした、が、しかし少女は一刀のもとに絶命し果てて
いた。
次の瞬間、フレイヤは愛馬にまたがり、手綱を引いた。
「フレイヤ、なぜだ・・・・・なぜユラを!!」
激しい憎悪と怒りの目がフレイヤに向けられた。
「私が憎い?キリオン・コンラート。憎みなさい、そして今度はお前が私を
追う番だ。」
ユラの骸をかき抱き、コンラートは低くつぶやいた。
「必ず・・・・・必ず殺してやる・・・・」
「待っているわ。」
フレイヤは悲しげに言った。
そして、右足を馬の腹に当てると、風のようにその場を走り去っていった。
(あの人は・・・・・・)
ジュヌバの少年シュクは思った。
(あの人はもしかしたら、コンラートを・・・・・・)
しかし、女戦士の心を理解するには、彼はあまりに幼かった。
薄雪草の綿毛が、再び風に舞い始めていた。